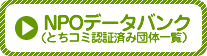能登地震・救援>>こちら



学生・若者ボランティア募集中。現在15人。
毎月1〜2回の会議で、当日までの企画を一緒に考えてくれる人募集中。
ボランティア大募集!
◎相談聞き取りボランティア
◎食品回収ボランティア
◆毎週木 15時~ フードバンク会議

2021-2022年度休眠預金活用制度における助成事業の実行団体の選定取消また全額返金請求について
NPO法人とちぎボランティアネットワーク「とちぎコミュニティ基金」は、休眠預金活用制度における助成事業の実行団体として採択、助成、支援を行った「栃木公立夜間中学校研究会」について、事業終了後に虚偽の報告、不正支出等が発見されたため、2024年5月9日、当該団体の選定の取り消し、助成金の全額返金の請求を行いましたことを報告いたします。
1.対象事業
2021年度 新型コロナウイルス対応支援助成事業(休眠預金活用事業)
実行団体名:栃木公立夜間中学校研究会(代表者 大橋衛 任意団体)
事業名:栃木夜間中学校設置推進PROJECT
事業期間:2022年6月1日~2023年2月28日
助成金額:2,000,000円
2.本件経緯と措置について
2022年3月16日 NPO法人とちぎボランティアネットワーク(以下、「当会」)とJANPIAとの資金提供契約締結後、4月5日~4月28日 実行団体の公募を行い、当該団体より助成金申請書の提出、受理、当会での審査を経て同年5月27日に採択通知、6月に資金提供契約(助成期間、2022年6月1日~2023年2月28日)ののち、当該団体の活動が開始されました。(助成金 200万円)
その後、事業完了となりましたが、2023年10月、当会に当該団体について不正の疑いについて外部関係者からの告発を受け調査を実施したところ、領収証の偽造等の疑いが明らかとなったことから、事業の選定取消が妥当と判断、本年4月に契約解除等に関する通知を行い、所定の手続きを経て選定取消の措置を講じました。
現在、支払い済みの200万円の助成金の全額返還を求めたものの、未だ返還には至っていないところ、本件への厳正な対応の必要性に鑑み、休眠預金活用事業の指定活用団体であるJANPIAとも協議の上、刑事告発を行うものとしております。
3.再発防止について
資金分配団体として、採択された実行団体において不正行為が発生したことは誠に遺憾であり、改めて当該実行団体選定から契約終了、現在までの状況を振り返り、発生の原因、どのような点に留意すれば再発防止につながるかなど十分に精査を行い、休眠預金活用事業の指定活用団体であるJANPIAにも報告し、再発防止に向けて取り組んでまいります。
障害(ハンディキャップ)を作り出しているのは「社会」かも。地域街で自立生活をする障害者の話

7月9日のみんながけっぷちラジオでは、NPO法人自立生活支援センターとちぎ(CILとちぎ)の齋藤康雄さん(55歳)をゲストに迎えた。CILとちぎは、どんなに障害が重くても自分らしく地域の中で生活できるように、当事者が中心となって運営しているNPOだ。齋藤さんは高校生の時にプールへの飛び込み事故で頸椎を損傷し、首から下が動かなくなってしまった。今回のラジオの事前取材では重度障害者でひとり暮らしをしていて、20年前に齋藤さんと一緒にCILとちぎを立ち上げた箱石充子さん(84歳)にもお話を伺った。
自分でヘルパーを探し・育てる「重度訪問介護」
箱石さんが自立生活を始めた30年前の宇都宮のヘルパー制度は、週2回で、1回1時間の支援だった。全身性の重度障害者には全く足りず、暮らせなかった。介助は継続的に必要であり、会社員のようなヘルパーの時間割では生きていけない。そこで1970年代から障害を持つ当時者たちが政府に抗議・要求して作ってきたのが「重度訪問介護」という制度だった。2000年代から生活圏の拡大を図るための援助を24時間、365日受けることができるようになった。
生活の介助なので、自宅での日常生活のサポートや外出時の移動介護もする。約3日間の簡易な研修でヘルパー3級の資格を取ることができる。CILとちぎは利用者(障害者本人)が自分に合ったヘルパーを推薦し、登録する「利用者が主宰者である介護事業所」なのだ。
「自立とは、依存できるものを増やすこと」
斎藤さんは「自立とは、依存できるものを増やすこと」という。高校・大学の頃、親しか日常生活の介助を頼めなかった。食事も風呂も外出も、学校への通学もノートテイクも・・・。制度がないからヘルパーがいなかった。学校での支援もなかった。だが、こうしたものを社会が準備すれば頼っていける。いろんなものに「依存できる」という。
障害(ハンディキャップ=社会的不利)は健常と対極に位置するのではなく、社会が作り出しているのかもしれない。例えば、健常者が買い物に行くとき、自転車やバスなどの手段に頼っている。つまり「健常者にとっての依存先」を作っているのだ。買う食べ物だって誰かが生産したモノであり、依存の幅が非常に多い。障害者はその選択肢が少なく、これは社会自体が障害(ハンディキャップ)を生みだしているともいえるのだ。
日本では、健常者と障害者の教室や学校を分けた教育が行われる。そのため、小さい頃から相互に関わる機会が少なく、理解が進まない故に偏見や差別がある。すべての子供たちが共に学び合うインクルーシブ(包摂的な)教育が必要であり、この教育が社会によって作られる障害を減らす一助になるかもしれない。
【ラジオ後記】実は箱石さんにインタビューをしたとき、私が考えていた質問項目に「施設ではなく自立を選んだ理由は?」というものがあった。しかしお話を聞いて、自立したいという気持ちに理由なんていらず、この質問自体が私の中に「障害者=誰かに支えてもらう」という偏見があると気づいた。誰もが「1人暮らしをしたい」「自分で自由に選択したい」と思うはずなのに、結果的に障害者を別で考えていたことを私自身が体現していたと非常に恥ずかしく思った。地域でパワフルに生きる人たちは齋藤さんや箱石さん以外にももっといるはず。いろんな人と関わって、誰もが暮らしやすい地域社会に私も貢献していこうと改めて思った。(ラジオ学生とま)
☆質問してみたい方はどんどんこちらまで⇒(773@miyaradi.com) ☆リスナーの皆さんのご意見・ご感想もお待ちしております! ★ミヤラジ(77.3FM)にて毎週火曜19:00~20:00オンエア! ★FMプラプラのアプリやブラウザからも聞けます(https://fmplapla.com/)
8/2(金)、8/3(土)与一まつりに出店しまーす!

開催時間:15時~20時頃
大田原市TOKOTOKO~多目的中央公園周辺で
たくさんのイベントと出店が出ますよ!
子どもの居場所 スマイルハウスも出店するよ
【たこ焼き、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい】
子どもたちに楽しんでもらうお祭りを盛り上げます!
たこやきボランティア募集中でーす!
楽しいので、ぜひ来てね!(しょうちゃん)